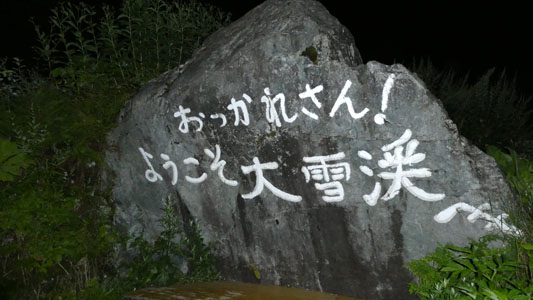 |
 |
| 白馬尻。テントが2張あった |
ケルン付近(標高1640m)に雪は皆無 |
 |
 |
標高1740m付近で雪渓登場。
でも秋道を進んで1860m付近で雪渓に乗ったら遅すぎた |
標高1950m付近で秋道登場。でも雪渓を登る |
 |
 |
| 標高2020m付近で秋道に乗った |
橋。水量は減っていた |
 |
 |
| 避難小屋 |
村営頂上宿舎前の水場。今年はいつまで雪が残るか |
 |
 |
| 村営頂上宿舎 |
ウルップソウの咲き残り |
 |
 |
| ミヤマキンポウゲ |
ミヤマクワガタ |
 |
 |
| 白馬山荘のシルエット |
白馬山荘 |
 |
 |
| 日の出待ちの人々 |
妙高山の右手から日の出 |
 |
 |
| 日の出を見つめる人々 |
白馬岳山頂 |
 |
| 白馬岳から見た360度パノラマ展望写真(クリックで拡大) |
 |
| 白馬岳から見た富山湾と能登半島。能登半島全体が見えたのは今回が初めて。 |
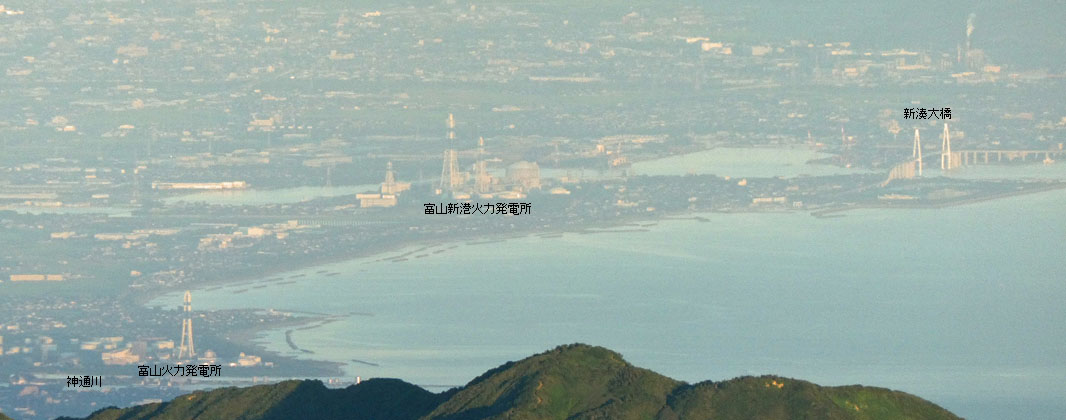 |
| 白馬岳から見た富山新港付近。火力発電所の巨大煙突が見えた |
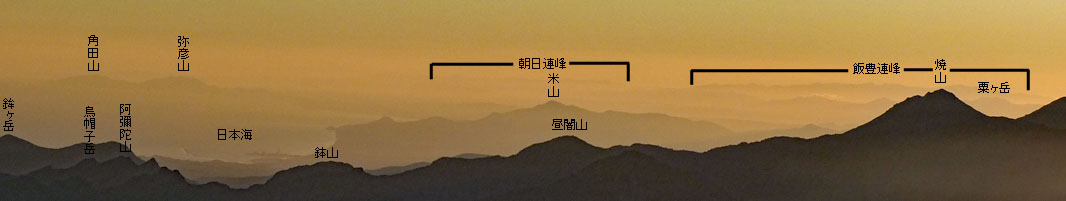 |
| 白馬岳から見た飯豊連峰(距離約210km)、朝日連峰(距離約255km) |
 |
| 白馬岳から見た朝日連峰(距離約255km) |
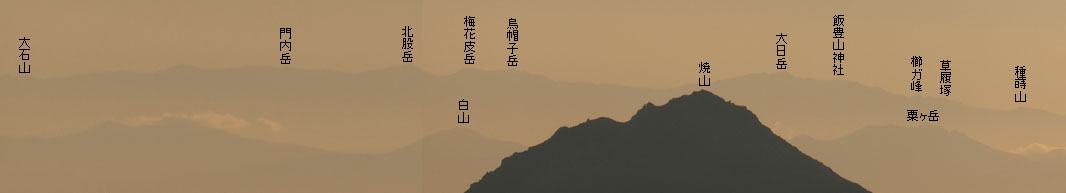 |
| 白馬岳から見た飯豊連峰(距離約210km) |
 |
| 白馬岳から見た村杉半島の山々 |
 |
| 白馬岳から見た利根水源山脈、尾瀬、奥日光の山々(クリックで拡大) |
 |
| 白馬岳から見た奥秩父 |
 |
| 白馬岳から見た南アルプス(クリックで拡大) |
 |
 |
| 白馬岳の影 |
黒部川河口 |
 |
 |
| 白山 |
下山開始 |
 |
| シコタンハコベ。花の形状は他に似た種類が多いが、葉の形状が独特なので葉で判別するのがいい |
 |
 |
| イワツメクサ |
チシマギキョウ |
 |
 |
| イブキジャコウソウ |
トウヤクリンドウ |
 |
 |
| タカネツメクサ |
ミヤマクワガタの実 |
 |
| おそらくカンチコウゾリナ。葉先が尖って葉側面の鋸歯が鋭い |
 |
| おそらくミヤマコウゾリナ。葉先が丸く葉側面の鋸歯がほとんど無い |
 |
 |
| イワギキョウ |
タカネシオガマ |
 |
 |
| ミヤマアケボノソウ |
ミヤマウイキョウ |
 |
 |
| ホソバツメクサ |
シコタンソウ |
 |
| シロウマオウギ。まだ咲いているとは思わなかった。花の色が真っ白で花の付け根に黒い毛があるのが特徴 |
 |
 |
| 下界のヒメジョオンみたいだがエゾムカシヨモギ |
たぶんタカネイブキボウフウ |
 |
 |
| トウヤクリンドウに似ているが背丈が高すぎる。シロウマリンドウっぽい |
ミヤマオトコヨモギ |
 |
 |
| ミヤマクワガタ |
ウメバチソウ |
 |
 |
| コマクサ |
タカネニガナらしい |
 |
 |
| 水源の雪渓 |
イブキトラノオでいいか |
 |
 |
| テント場 |
旭岳 |
 |
 |
| 細かな種類は分からないがコゴメグサ |
タカネヨモギ |
 |
 |
| 葉先が丸いのでミヤマコウゾリナっぽい |
ウサギギク |
 |
 |
| ヒメクワガタ |
ミヤマアキノキリンソウ。多数見られる |
 |
 |
| ミヤマリンドウ。チングルマに埋もれて生えている |
ハクサンフウロ |
 |
 |
| このお花畑はトリカブトが中心 |
村営頂上宿舎前から見下ろす |
 |
 |
| 調査の結果、オノエリンドウっぽい。初めて見た |
クモマミミナグサ |
 |
 |
| イワオウギ。実が付いていた |
ハクサンフウロのお花畑 |
 |
 |
| ヨツバシオガマの実。袋状に丸く膨らんでいる |
こんなところにもミヤマアケボノソウ |
 |
 |
| ミヤマアカバナかシロウマアカバナ |
細かな種類は分からないがトリカブト |
 |
 |
| 沢沿いにはメタカラコウ |
ヨツバシオガマ |
 |
 |
| タカネナデシコ |
ミソガワソウ |
 |
 |
| クルマユリ |
オニシモツケ |
 |
 |
| 杓子岳と避難小屋 |
小雪渓 |
 |
 |
| イワオウギ |
ヒメクワガタ |
 |
 |
| ミヤマタネツケバナ |
オオバミゾホオズキ |
 |
 |
| 小雪渓付近はミヤマキンポウゲを中心とするお花畑 |
ミヤマキンポウゲ |
 |
 |
| 標高2370m付近 |
標高2320m付近 |
 |
 |
| たくさんの登山者とすれ違う |
シロウマアサツキ |
 |
 |
| 標高2300m付近 |
キバナノカワラマツバ |
 |
| 先頭がルートを間違えたのか後続も大雪渓末端まで登ってきている。末端付近は既に雪が薄く、いつ崩壊しても不思議ではなく非常に危険 |
 |
 |
| 左岸秋道 |
標高2160m付近 |
 |
 |
| 標高2070m付近 |
ウサギギク |
 |
 |
| ウルップソウ |
標高2020m付近。ここが今の秋道取付 |
 |
 |
| 大雪渓から秋道に乗り換えて登る人々 |
大雪渓に乗ると風が涼しい! |
 |
 |
| 次々と登ってくる |
標高1860m付近 |
 |
 |
| 標高1830m付近 |
標高1800m付近が大雪渓乗換場所 |
 |
 |
| 秋道を下る |
短い雪渓横断。往路では秋道で高巻きした |
 |
 |
| 標高1730m付近。大勢の登山者がアイゼン装着中 |
大雪渓を見上げる |
 |
 |
| ヤマガラシ |
オニシモツケ |
 |
 |
| ミソガワソウ |
おそらくメタカラコウ |
 |
 |
| 標高1700m付近 |
ミヤマカラマツ |
 |
 |
| 標高1680m付近 |
オオバミゾホオズキ |
 |
 |
| ミヤマアカバナだと思う |
ニガナ |
 |
 |
| シロバナニガナ |
タテヤマウツボグサ |
 |
 |
| オオレイジソウ |
白馬尻 |
 |
 |
| 白馬尻から見た大雪渓 |
こんな場所でもエゾシオガマ |
 |
 |
| クロバナヒキオコシ。初めて見た |
アジサイ |
 |
 |
| 林道終点 |
ヨツバヒヨドリ |
 |
 |
| テンニンソウかフジテンニンソウ |
長走沢で水浴び |
 |
| 林道から見た白馬岳。ズームで山頂の人の姿が確認できた。逆に言えば山頂から林道が見える |
 |
 |
| メタカラコウ。標高が高いものと比較して花の穂が長い |
ソバナ |
 |
 |
| 車が上がっていった |
林道のショートカット道上部入口 |
 |
 |
| ショートカット道。明らかに道 |
林道のショートカット道下部入口 |
 |
![]() |
| 猿倉第一駐車場。第二駐車場も満車だった |
|